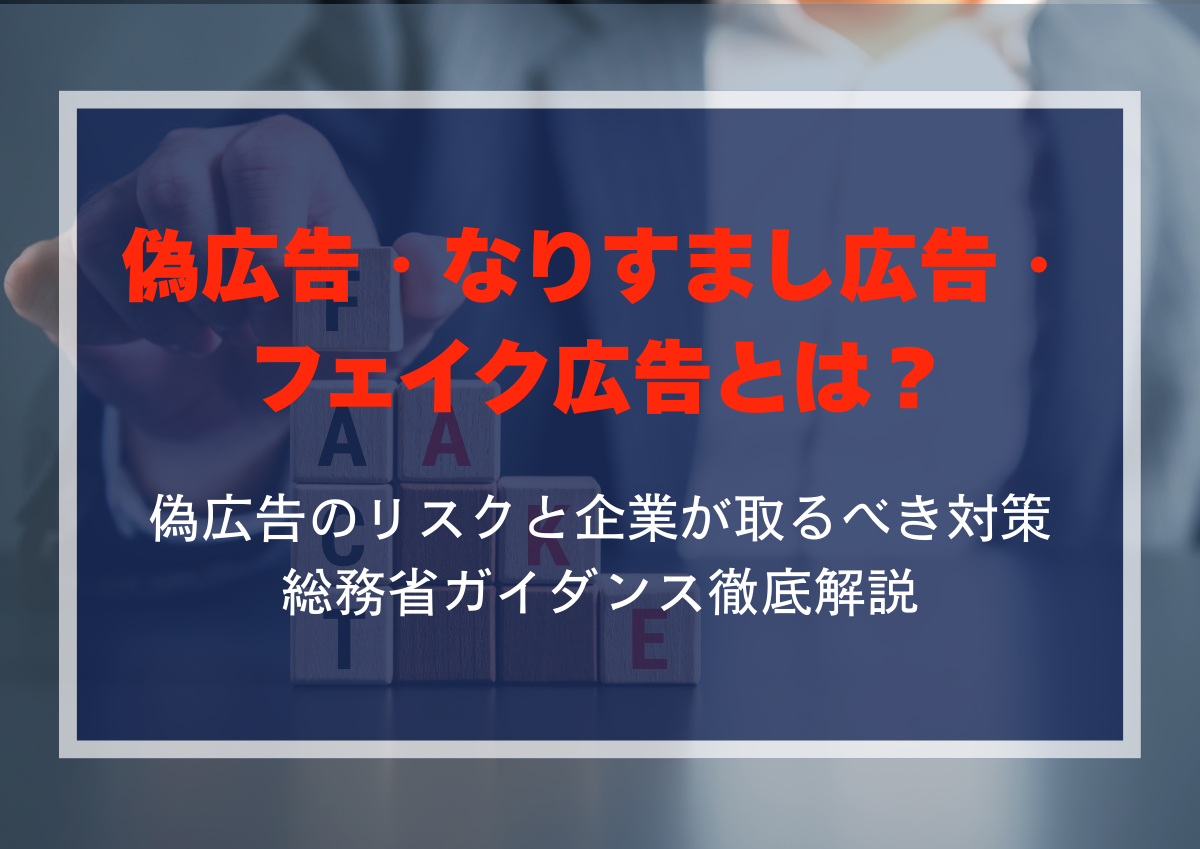近年、SNSやウェブ広告で急増しているのが「偽広告」です。著名人の写真や企業ロゴを無断で使い、投資詐欺や偽通販サイトへ誘導する悪質な手口が社会問題化しています。総務省もガイダンスを公表し、広告主にリスク対応を求めています。本記事では、偽広告の実態と企業が取るべき体制、さらに契約段階から防ぐ方法をわかりやすく解説します。
ネット上の誹謗中傷にお困りではありませんか?
対策実績20,000件以上のWebリスクサービスの概要・料金が分かる資料はこちら
なぜ「偽広告」がいま問題なのか
インターネット広告は日本国内で巨大市場に成長し、検索・SNS・動画・ディスプレイなど多様なチャネルで配信されています。運用型広告は「少額から始められ、効果検証もしやすい」点が魅力ですが、同時に流通の複雑化や媒体の玉石混交化が進み、偽広告の温床になっている面も否めません。偽広告は、ユーザーを欺く意図で作られた広告だけでなく、広告主の意思に反して誤解を与える配信も含む広い概念です。つまり、「ウソの広告」だけではなく、「ウソの環境に載った広告」も企業の評判を損ないます。
総務省のガイダンスはこの状況を踏まえ、広告主が「成果効率」と同じレベルで「広告品質」を管理することを強く求めています。広告はもはや獲得のためのスイッチではなく、企業の信頼を支えるインフラ。偽広告の放置は、短期のCPAが良くても長期の信頼低下で必ず跳ね返ってきます。
偽広告(なりすまし広告・フェイク広告)とは?代表的な種類と見分け方

一口に偽広告といっても実態はさまざまです。ここでは現場で遭遇しやすい代表例を整理します。タイプ別に兆候(シグナル)も付記するので、企画・運用・監査の場でお役立てください。
- なりすまし広告:著名人や企業のロゴ・写真を無断使用し、本人推薦を装う。
- 兆候:本人や企業の公式発信と整合しない文言/異様に高い利回り訴求。
- 詐欺誘導広告:「必ず儲かる」「今だけ」などの極端な表現で外部の詐欺LPへ誘導。
- 兆候:ドメインが頻繁に変わる/事業者情報の欠落。
- フェイクニュース拡散型:虚偽記事の体裁で広告を埋め込み信憑性を偽装。
- 兆候:出典が不明瞭/引用が自己循環。
- 権利侵害型:肖像・著作物を無断利用して商品・サービスを販売。
- 兆候:著作権表示なし/問い合わせ先が匿名。
- ディープフェイク活用:合成音声・映像で本人発言を偽装。
- 兆候:音声と口の動きのズレ/不自然な瞬き。
- クローキング/ミラーLP:審査用と配信用で内容を差し替え、規約回避。
- 兆候:UAや地域でLP内容が変化。
- アドスタッフィング:見えない位置や短時間に大量配信し、偽の成果を水増し。
- 兆候:ビューアビリティが異常に低い/IVTが高止まり。
社会的にも「著名人写真の無断使用による投資詐欺型」の被害は繰り返し報じられています。本人無関与でも信じてしまう人が少なくないこと、削除しても新規クリエイティブが次々出回ることから、個社だけでは完全に抑え込めない難しさがあります。
偽広告が企業にもたらす主要リスク
ブランド毀損と信頼の劣化
不適切なコンテンツや偽情報の隣で広告が表示されると、「この会社はこういう場に広告を出すのか」という認知が形成されます。スクリーンショットは一瞬で拡散し、火消しより先に評判が先行します。採用や投資家の目も厳しく、誤配信のコストは広告費以上に大きくなりがちです。
広告費の不正流出(アドフラウド)
ボットや不審サイトへの配信は、クリックやCVの見かけを膨らませますが売上に跳ねません。さらに学習アルゴリズムが誤ったシグナルを拾い、健全な面への配信が抑えられる副作用もあります。早期にIVTやビューアビリティを抑えることは、単なる「守り」ではなく「攻めの効率化」に直結します。
不健全なエコシステムへの加担とCSR問題
広告費はメディアの血流です。違法・不適切なメディアに広告が出れば、その運営を資金面で支える結果になります。CSR・コンプライアンスの観点からも、放置は許されません。公共機関や上場企業では説明責任も問われます。
総務省ガイダンスが示す「偽広告」対応の方向性
経営層の関与―効率と品質の両立を意思決定する
ガイダンスは、現場の運用最適だけでは解決できないと明言しています。CPAが一時悪化しても不適切面を止めるべきときがあり、その判断は経営の役割。広告品質のKPIと投資方針を経営会議レベルで定義し、リソースと権限をセットで付与しましょう。
契約段階の対策―配信前にルールで守る
偽広告を「配信後に消す」体制は限界があります。RFP・契約・SLAの段階で、配信面の可視化、第三者計測、違反時の遮断・返金、ブロックリスト運用、ログ保全・監査受入れ等を明文化し、代理店・媒体と共通の土台をつくることが推奨されます。
技術的対策と運用管理―ツール×プロセスの二段構え
アドベリフィケーション(ビューアビリティ/IVT/ブランドセーフティ)による常時監視と、プラットフォームの除外設定(カテゴリ・キーワード・プレースメント)が基本線となります。さらにPMP等のクローズド枠や信頼できる媒体への重心移動でリスクを下げましょう。月次のポストモーテムと異常時の即応フローが継続改善の要です。
企業がとるべき体制構築のステップ
ステップ1:責任体制とエスカレーションの明確化
マーケ(運用)・法務(表示/契約)・広報(ブランド)・情報セキュリティ(ログ/監査)で横断チームを設置。重大事案の連絡先を一本化し、夜間・休日を含む対応窓口も明示します。指揮系統の曖昧さは対応の遅れに直結します。
ステップ2:自社リスクの棚卸しと優先度設定
金融は誤認防止、医療・健康は薬機法、サブスクリプションは解約動線や料金表示と産業ごとに急所は違います。自社の「致命傷になりうる」リスクを特定し、閾値と対処方針を先に決めておくのがコツです。
ステップ3:広告管理方針とレビュー基準の策定
「出稿可・不可の媒体カテゴリ」「NG表現」「レビューのレベル(一次/二次/臨時承認)」を文書化。担当が変わっても品質がブレない仕組みをつくります。テンプレ化・チェックリスト化は現場の負担を大きく減らします。
ステップ4:契約書・SLAへの落とし込み
計測必須項目、開示範囲、レポート頻度、アラート基準、遮断と補填、監査対応、データ保持期間などを契約に書面化。期待水準を共有し、運用上の解釈のズレを潰しておきます。
ステップ5:モニタリング運用と継続改善
週次レビュー(異常検知/遮断判断)と月次ポストモーテム(KPIと学びの共有)を定例化。ブロック/セーフリストの更新も運用の一部に組み込みます。改善は「イベント」ではなく「習慣」に。
偽広告対策に必要な「品質管理指標」
ビューアビリティ―見られていない広告は存在しないのと同じ
一定のピクセル/秒数を満たした表示率。低い面は配信停止・入札調整。媒体・フォーマット別の基準を持ち、改善余地が乏しい面は割り切って撤退します。可視率が上がると、学習も安定します。
IVT率(無効トラフィック)―誤学習の原因はここに潜む
ボット、スパム、アドスタッフィング等。閾値と遮断フローを事前定義し、異常時は媒体と原因究明・代替配信を即協議。IVTを抑えた面に配信を寄せるとCVの質とLTVが改善します。
ブランドセーフティ指標―表示先の「隣人」を管理する
ヘイト・違法・成人・暴力・誤情報などカテゴリ別の表示状況。禁止カテゴリと例外承認のプロセスを決め、違反検知から遮断までのSLA(目標時間)を設けます。ホワイトリスト運用は強力な選択肢です。
ユーザビリティ評価―短期のCTRより長期の信頼
誤クリック誘導、偽装UI、過剰オーバーレイなどは、短期の数値を良く見せても長期の解約・離反を招きます。苦情件数・直帰率・NPSなどの補助指標で追跡し、表現とLPの動線も一体で見直します。
偽広告の事例紹介
社会的には、著名人の顔写真を無断使用し、投資詐欺LPへ誘導する偽広告が繰り返し問題化しています。本人や企業が否定しても、クリエイティブは次々生成・拡散され、完全な封じ込めは容易ではありません。ここから言えることは、「配信後の削除中心」から「配信前の予防+配信中の常時監視」へ軸足を移す必要があるということです。
ケース①大手メーカーとの共同開発を装う偽広告
猛暑を背景に、サーキュレーターや携帯扇風機をアイリスオーヤマや東京科学大学などの大手メーカーや大学と共同で開発したとうたう偽広告がSNSや動画サイトで拡散。実際にはこれらの広告は名前が使われた企業や大学とは関係がなく、省エネ大賞など受賞マークも虚偽でした。購入者からは「広告と違う商品が届いた」との相談も寄せられています。関連とされた企業は無関係を表明し、消費者庁も誇大表示に注意を呼びかけています。
ケース②オムロン・アンビー製品を装った偽広告
「オムロン」「アンビー」をかたったスマートウォッチやイヤホンの広告がSNSに掲載され、模倣品が届く被害が増加。全国で相談が100件超寄せられています。偽サイトは「極端な安さ」「支払い方法の限定」「事業者情報の不備」が特徴。消費者庁は正規ルートでの購入を呼びかけています。
ケース②証券業協会による偽広告注意喚起
SBI証券、楽天証券などの証券会社や日本証券業協会を名乗る偽アカウント・広告がSNSやSMSで拡散。アクセスすると個人情報や資金を詐取される可能性があります。特徴は「必ず儲かる」などの誇大表現や不審なURL。日本証券業協会は公式情報の確認と、不審広告をクリックしないよう注意を促しています。
現場が今日からできる偽広告対策チェックリスト
- 禁止カテゴリ/セーフ・ブロックリストを最新化したか
- 第三者計測の導入と、週次・月次のレビュー枠を確保したか
- IVT・ビューアビリティの閾値と遮断SLAを定義したか
- RFP/契約/SLAに品質要件を明文化したか
- 重大インシデント時のエスカレーション連絡網を整備したか
- クリエイティブとLPの整合(料金・制約・根拠表示)を点検したか
- 媒体別の学びをナレッジ化し、次配信へ反映したか
当社サービス「AdTRUST」で実現できること
契約段階の支援:守りを前倒しに設計する
調達仕様書・契約書・SLAに盛り込むべき品質要件の雛形を提供。配信面開示、第三者計測、アラート基準、遮断・補填、ログ保全、監査受入れまで、「後で揉めない」ための文言を整えます。公共・上場水準のドキュメント化にも対応します。
広告審査・ガイドライン適合チェック:偽広告に“しない”表現へ
景表法・薬機法・特商法・各業界ガイドラインに照らして出稿前チェック。誤認・誇大・紛らわしいUI(ダークパターン)を排除し、LPとの整合・根拠の明確化まで伴走します。
配信先リスクの監視:可視性と無効を二重で見る
第三者計測のログをレビューし、IVT・ビューアビリティ・ブランドセーフティの3指標を監視。閾値超過時はブロック/代替面提案まで迅速にサポートします。セーフ/ブロックリスト運用も実装します。
経営層へのレポーティング:効率と品質の二軸ダッシュボード
CPA・ROASと、IVT・可視率・違反面件数・UX苦情を同一ダッシュボードで可視化。重大事案の経過・再発防止策・来期の配分方針を資料化し、取締役会・経営会議での意思決定を後押しします。
よくある質問(FAQ)
Q1:ツールを入れたら偽広告はなくなりますか?
いいえ。ツールは「見る」道具です。契約・方針・運用の三点セットで初めて効きます。ツール導入=ゴールではありません。
Q2:成果が落ちるのが心配です
初期はCPAが一時的に上がる場合がありますが、中長期でCVの質・LTV・ブランド信頼が改善し、総合効率は向上する傾向があります。誤学習の除去は攻めの効率化です。
Q3:小規模チームでもできますか?
できます。レビュー基準のテンプレ化と週次の小さな回しが重要です。外部パートナーと役割分担すれば、少人数でも運用可能です。
より詳しいサービスに関する情報はこちらをご確認ください。
まとめ:偽広告対策を「現場任せ」から「経営主導」へ
偽広告は、ブランド・財務・CSR・法務の境界を越える経営課題です。総務省ガイダンスが示す通り、契約段階からの予防設計、第三者計測による常時監視、そして効率と品質の両立を経営が意思決定することが不可欠です。今日の1クリックは、明日の信頼に直結します。
自社だけで全方位の対策を回すのが難しいと感じたら、AdTRUSTをご検討ください。契約・審査・監視・経営レポートまでを一気通貫で伴走し、偽広告リスクから企業と生活者の信頼を守ります。