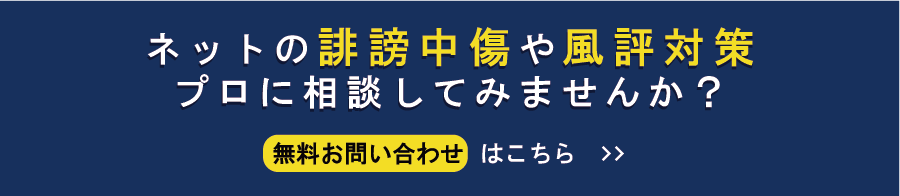レピュテーションリスクとは、企業や個人に関する悪評や否定的な情報が広まり、信頼や評価が損なわれるリスクのことです。
スマホやSNSの普及により、炎上や誤情報が一瞬で拡散し、売上低下やブランド毀損といった深刻な影響を及ぼすケースが増えています。こうしたリスクは表面化してからでは手遅れになることも多く、兆候段階で察知し適切に対策することが重要です。
本記事では、その仕組みや具体的な対策方法をわかりやすく解説します。
ネット上の誹謗中傷にお困りではありませんか?
対策実績20,000件以上のWebリスクサービスの概要・料金が分かる資料はこちら
レピュテーションリスクとは
レピュテーションリスク(reputation risk)とは、企業に対する否定的な印象や評判が広がることで、信頼性やブランドの価値が損なわれ、経済的な損失を招くリスクのことです。レピュテーション(reputation)は、日本語で評判や名声などと訳されます。一方、リスク(Risk)は恐れや危険という意味のため「評判の危険」が直訳といえるでしょう。
レピュテーションリスクのわかりやすい事例としては、いわゆるバイトテロが挙げられます。SNSでアルバイトが悪ふざけする様子を発信された結果、世間一般に悪評が広まり、結果として休業や廃業に追い込まれる企業も多いです。
そのため、レピュテーションリスク対策は、すべての企業において重要な課題といえます。
関連記事:レピュテーションリスクの事例から学ぶ損失とリスク回避のための対策を解説!
レピュテーションとブランドの違い
レピュテーションと混同されがちな言葉がブランドです。ブランドは企業や商品、サービスのイメージ、価値を具現化したものだといえます。
そのため、ブランドという言葉は、競合他社との差別化を目的とする際に用いられることが一般的です。言い換えれば、企業が世間に見られたい姿や「こうありたい」と思う姿がブランドだといえるでしょう。
それに対してレピュテーションは評判や名声という意味なので、企業や商品、サービスが世間から見られた・評価された結果だといえます。
したがって、ブランドが企業の理想とする姿で、レピュテーションは世間一般のありのままの姿だという点が、両者の違いです。また、ブランドはポジティブなイメージですが、レピュテーションにはポジティブとネガティブの両方が包含される点も違いといえます。
レピュテーションリスクが注視されるようになった背景
SNSが発展したことで、自社にとってネガティブな情報がすばやく拡散されるようになったことが、レピュテーションリスクが注視されるようになった背景にあります。
1人1台のスマホが当たり前の時代になったことによって、SNSの利用者も飛躍的に増えました。そのため、自社にとってネガティブな情報が拡散するスピードも速くなっており、「気づいたときには炎上していた……」というケースも珍しくありません。
SNSの中でも特にTwitterは情報の拡散スピードが速いので、たとえ事実無根の誹謗中傷であったとしても、瞬く間に広がってしまう恐れがあります。自社やサービス、商品に対する誹謗中傷を放置すると、企業の収益悪化や顧客・取引先の信用を失う可能性があるため、早めに対処しなくてはいけません。
さらに、ネット上に拡散された情報は半永久的に残りますので、ネガティブな影響を受ける期間が長くなることも肝に銘じておく必要があります。レピュテーションリスクは一度発生すると、元の状態に戻すことが非常に困難なので、未然に防ぐことが大切です。
レピュテーションリスクが顕在化する主な原因

レピュテーションリスクを引き起こす原因は、さまざまあります。どのようなものがリスクにつながるのかを把握しておくことで、レピュテーションリスクの発生を未然に防ぎやすくなるでしょう。
従業員の不祥事
正社員や派遣社員、アルバイトなどの従業員が起こした不祥事によって、レピュテーションリスクにつながるケースは非常に多いです。
例えば、バイトテロが原因でレピュテーションリスクが発生し、営業停止や廃業に追い込まれた飲食店の事例がわかりやすいでしょう。従業員の無責任な行動によって、大きなダメージを被った企業は後を絶ちません。
そのため、社員としての行動規範や禁止行為に対する罰則などを明示化するなど、社内のコンプライアンスやガバナンスの強化が、レピュテーションリスクの抑制には有効です。
経営陣の不祥事
経営陣の不適切な発言や行動が報道されることによって、レピュテーションリスクが発生するケースもあります。
例えば、経営陣の不倫や脱税、横領などが代表的です。また、インサイダー取引やマネーロンダリングなどの違法行為も、レピュテーションリスクの要因になりえます。
不適切な経営陣が経営する企業は、社会から大きな反感を買う可能性が高く、顧客やステークフォルダの信頼を失う事態に発展する可能性が高いです。
質の悪い製品やサービス
自社の商品やサービスに対して顧客からクレームが入ったり、悪評がSNSで拡散したりすることによっても、レピュテーションリスクは発生します。
例えば、質の悪い製品やサービスを提供することによって、「〇〇最悪」「〇〇は不味い」といった評判が広がることで購入や利用を控える顧客が増え、収益に深刻なダメージを与えるでしょう。たとえ事実無根の誹謗中傷だったとしても、悪評として広がった結果、レピュテーションリスクに発展する可能性もあります。
根拠の薄い不当な風評被害
SNSなどに事実ではない情報が出回り、風評被害が拡大するのもレピュテーションリスクの原因となります。
企業や個人が不祥事を起こした場合はもちろんですが、事実無根の情報や誤解に基づく噂がSNSや口コミサイトを通じて瞬時に拡散されることがあります。特に、感情的に共感を呼ぶ内容やセンセーショナルな情報は、真偽を問わず多くの人の関心を引くため、拡散のスピードが加速します。
一度広がった風評は、後から訂正情報を発信しても完全に払拭するのが難しく、企業の信頼やブランド価値に長期的なダメージを与える可能性があります。こうしたリスクを未然に防ぐためには、日頃から正確な情報を発信し、誤解を招く余地を減らす努力が求められます。また、万が一風評が発生した場合には、迅速かつ誠実な対応が信頼回復のカギとなります。
内部告発
劣悪な労働環境や、違法な経営をしていることなどを、従業員が内部告発することによってレピュテーションリスクが発生するケースもあります。
表からはクリーンな会社にみえても、内部では長時間残業やパワハラなどが横行する企業は、残念ながら多いものです。このような企業でレピュテーションリスクが発生すると、顧客やステークフォルダからの信用はもちろん、今後の採用活動にも大きな影響を与えるでしょう。
少子高齢化の影響で労働人口が減少している現在、優秀な人材を雇用できなくなることは、継続的に事業活動ができなくなるリスクにもつながります。
行政処分
行政処分の対象になることによって「コンプライアンスが徹底されていない企業」というイメージが社会に浸透し、レピュテーションリスクが発生することは、よくあるケースです。
例えば、違法な事業や取引を行った結果、監督官庁による行政処分や指導を受けた企業は、社会的な信用を失う可能性が高くなります。その結果、ブラック企業や悪徳企業といったレッテルを張られ、企業活動に大きなダメージを被ることでしょう。
そのため、企業内のコンプライアンスを強化することによって、行政処分や指導を受けない企業体質にしておくことが求められます。
レピュテーションリスクの具体事例
レピュテーションリスクによって企業がどのような被害を受ける可能性があるのか、具体的な事例を確認しておきましょう。
某ピザチェーン店におけるレピュテーションリスクの事例
某ピザチェーンにおいて、アルバイトがシンクや冷蔵庫の中に入った写真がSNSに投稿され、ネット上に拡散され、「不衛生だ」と大炎上する事態にまで発展しました。さらに、隣接するスーパーの陳列棚の上でいたずらをしている写真が拡散し、同店舗に迷惑をかけるという二次被害も発生したそうです。
その結果、同ピザチェーンを運営していた企業は2億円以上の負債を抱え、倒産へと追い込まれました。また、アルバイトの通っていた高校が特定されたことで、学校側も謝罪させられるという事態にまで発展した、最悪ともいえるバイトテロの事例です。
某そば屋におけるレピュテーションリスクの事例
某そば屋で働いていたアルバイトが、Twitterで「洗浄機で洗われてキレイになっちゃった」と写真付きの投稿をしたことで、瞬く間に拡散され炎上しました。具体的にはキッチンに置いてある洗浄機の上に乗る、シンクに足を突っ込む、半裸の上半身にお客さまへ出す茶碗を置く写真などが投稿され、顧客から多くのクレームが寄せられたそうです。
同店はこのバイトテロによって3,300万円もの負債を背負い、倒産に追い込まれました。また、同店の経営者はバイトに対して訴訟を起こし1,385万円の損害賠償を要求しましたが、裁判所の提案によって結局200万円で和解することになったそうです。
なお、同店は創業者が他界したばかりで、その妻が再建に奮闘していました。しかし、レピュテーションリスクが発生したことで、その希望は無残に消え去りました。
某通信教育・出版企業におけるレピュテーションリスクの事例
子どもや学生向けの通信教育サービスや教材を提供する某企業において、3,500万件もの個人情報が関連するシステム会社から流出したことがありました。システム会社の派遣社員が、個人情報を名簿会社に販売していたことが原因です。
このレピュテーションリスクが発生したことで、取締役2名の解任と、深刻な顧客離れによって大赤字へと転落しました。レピュテーションリスクは社内だけではなく、関連会社やステークフォルダが原因で発生することもある事例といえるでしょう。
某広告代理店におけるレピュテーションリスクの事例
某広告代理店に働く新入社員が、度重なる残業によってうつ病を発症し、自殺してしまう事件が起こりました。同企業には慢性的に長時間残業を行う企業文化があり、過去に社員が自殺した経緯もあったそうです。そのため、ネットだけでなくマスメディアでも大きく取り上げられる事態に発展しました。
自殺した社員の両親が同企業を訴えた結果、最高裁が安全配慮義務違反を認定し、約1億6,800万円の損害賠償を支払い和解する事態に発展しています。同企業は多くのクライアントからの信頼を失ったことに加え、同企業の案件を受託することによって「労働基準監督署に査察されるのでは?」と取引を避ける企業も現れたそうです。
同事件は企業の不適切なコンプライアンスが原因で、発生したレピュテーションリスクだといえるでしょう。
レピュテーションリスクによって生じる被害
レピュテーションリスクが生じることによって、企業はさまざまな被害を受けるでしょう。本章では、代表的なレピュテーションリスクによる被害を3つ紹介します。
収益の悪化
レピュテーションリスクによる被害の代表的なものが、収益の悪化です。
自社の商品やサービスに関するネガティブな情報を拡散するレピュテーションリスクが生じると、顧客が購入や利用を避けるようになります。その結果、企業の収益が悪化する可能性は高くなります。また風評被害によって、競合他社に市場のシェアを奪われることもありえます。
離職率の上昇や採用が困難になる恐れがある
レピュテーションリスクにより、優秀な人材の採用が困難になる可能性があります。多くの求職者は、応募前に企業の評判や口コミをインターネットで確認するため、ネガティブな評価が広まっている企業は敬遠されがちです。
企業イメージが良好であれば問題はありませんが、ひとたび悪い評判が広がると、それを払拭するのは容易ではありません。否定的な情報を目にした応募者がエントリーを見送ったり、選考を辞退したりするケースもあり、結果として優秀な人材の確保が難しくなるリスクがあります。
さらに、こうした評判は社内の従業員にも影響を与える可能性があり、職場に対する不安や不満が増すことで、離職率が上昇する恐れもあります。外部からの信頼を失うだけでなく、内部の人材流出にもつながりかねないため、レピュテーションリスクへの対策は非常に重要です。
信頼回復のための甚大なコストが発生する
レピュテーションリスクによって失った信頼を回復するためには、広告宣伝やコンプライアンス遵守に甚大なコストが発生します。
特に刑事罰や業務停止命令、免許停止など、行政処分の対象になると信頼回復に時間がかかるため、なんとしても回避したいところでしょう。顧客やステークフォルダの信頼を失い、売上が減ったり取引が中止されたりすると、企業存続の危機に発展する可能性もあります。
レピュテーションリスクの対策方法
レピュテーションリスクへの対策として、まずは事前に回避する対策を取ることが重要です。また、リスクが顕在化してしまった際には、被害を拡大させないためにも別途対策を行う必要があります。
レピュテーションマネジメントの具体施策
以下の2つを紹介します。
- レピュテーションリスクを未然に回避するための施策
- レピュテーションリスクが顕在化した場合にとるべき施策
レピュテーションリスクを未然に回避するための施策
レピュテーションリスクを未然に防ぐためには、以下のような方法が挙げられます。
- 従業員教育の徹底
- 労働環境の改善
- 商品・サービスの質の維持・向上
- 経営状況の改善
- 広報活動の強化
- 怪しい企業や人物の調査
- 誹謗中傷対策の実施
- クライシスコミュニケーション対策
それぞれの方法の詳細については、以下の記事で解説しているのであわせてご確認ください。
関連記事:レピュテーションリスクを回避する8つの方法について徹底解説!
レピュテーションリスクが顕在化した場合にとるべき施策
レピュテーションリスクが発生した際は、まず状況を正確に把握し、原因を特定します。また、速やかに正しい情報を公表し、関係先との交渉や逆SEO対策を行います。さらには、再発防止策やSNS・アンケートによる評判の把握も大切です。
レピュテーションリスクの測定方法
企業はどのようにして自社の評判を把握すればよいのでしょうか。レピュテーションリスクを客観的に評価するためには、いくつかの手法があります。
たとえば、大手企業であれば「就職したい企業ランキング」や「ブラック企業ランキング」など、外部機関やメディアによる調査結果を参考にするのが有効です。こうしたランキングは、広く一般に認知されているため、企業イメージを測る指標として一定の信頼性があります。
一方で、中小企業やスタートアップ企業の場合、こうしたランキングに取り上げられる機会は少ないため、取引先・顧客・株主などのステークホルダーに対してアンケートを実施し、企業への信頼度や印象を把握する方法が効果的です。直接の関係者からの評価は、企業活動の改善やリスク管理に役立つ貴重な情報源となります。
レピュテーションリスクに対する保険もある
レピュテーションリスクに備える手段の一つとして、専用の保険商品が存在します。テレビや新聞などのマスメディアによる報道をきっかけに企業イメージが損なわれた場合、その対応にかかる費用をカバーするものです。具体的には、広報対応を依頼するPR会社への相談料や、事態の収束に向けた施策の費用などが補償の対象となります。
また、保険の内容によっては、実際にレピュテーションリスクが表面化した後の対応費用にとどまらず、ネガティブな情報が公表される前の対策費を補償するプランも用意されています。
レピュテーションリスクは未然に防ぐことが大切

レピュテーションリスクが発生した企業は、社会や顧客からの信頼を失い、収益やブランドに大きなダメージを受けます。一度失った信頼を取り戻すのは至難の業といえるため、レピュテーションリスクを未然に防ぐ取り組みが、すべての企業において重要な課題です。
なお、エフェクチュアルでは、レピュテーションリスクを抑制するWebリスクの解決サービスを提供しています。具体的には、検索エンジンの入力補助・関連検索に表示される、誹謗中傷キーワードを対策するネガティブキーワード対策サービスと、独自開発した誹謗中傷対策ツールの「Webリスククラウド」です。
ネガティブキーワード対策サービスは、風評被害につながる誹謗中傷キーワードを独自のモニタリングシステムにより早期発見し、レピュテーションリスクの抑制につなげます。また、Webリスククラウドを活用することによって、検索結果上の誹謗中傷サイトや、入力補助・関連検索の誹謗中傷キーワードを検知しアラート通知することが可能です。
エフェクチャルのWebリスクの解決サービスは、700社以上のWebリスク解決実績があります。ぜひお気軽にご相談ください。
エフェクチュアルのWebリスク解決サービスについて今すぐ確認する