SNS炎上は企業にとって大きなリスクです。この記事では、炎上の原因や事例を分析し、未然に防ぐ方法と対策を解説します。具体的には、
– 炎上リスクを抑えるポイント
– 高効果&リスク回避の投稿術と活用方法
– ユーザーとの適切なコミュニケーション
– 公式アカウントの運用ルールと教育体制
などを詳しくご紹介します。さらに、炎上発生時の対処法や事後対策、モニタリングツールの活用法もまとめています。この記事を読むことで、SNS炎上のリスクを最小限に抑え、安心してSNS運用に取り組むことができるようになります。
ネット上の誹謗中傷にお困りではありませんか?
対策実績20,000件以上のWebリスクサービスの概要・料金が分かる資料はこちら
SNS炎上対策を企業がする必要性とは?
日常生活において欠かせないコミュニケーションツールとなっているSNS。X・facebook・Instagramなどの普及率は年々増加していて、ICT総研の調査によると2026年末には国内ネットユーザーの80%以上がSNSを利用しています。SNSが社会に与える影響も大きくなっており、炎上により企業や社員などが被害を受けるケースも少なくありません。なかにはSNS上での誹謗中傷によって自ら命を断つケースや、大幅に売上が低下するケースなどもあり、今後ますますSNS炎上に対策する重要性は増していくことでしょう。
SNS炎上の原因と原因別の炎上事例
適切なSNS炎上対策を取るうえで、まずは炎上を引き起こす主な原因と過去の事例を確認しておきましょう。
①企業アカウントで個人的な見解を発信してしまう
社員が企業アカウントを使って個人的な見解を投稿してしまうことは、SNS炎上のよくあるケースのひとつです。企業アカウントは個人アカウントより規模や影響力が大きく、思いもよらないスピードで拡散される場合があります。1つの投稿が企業イメージを大きく左右する可能性があるので、投稿前には一度立ち止まって内容を精査する必要があります。
事例:【他社批判】家電販売企業による炎上事例
ある家電販売企業の公式SNSアカウントが、他社の復刻ゲーム機に対して「価値ゼロ」と明言した投稿を行い、大きな炎上を引き起こしました。
企業の公式アカウントという立場であるにもかかわらず、個人的な評価や感情を公に発信してしまったことが炎上の原因です。公式アカウントの発言は企業全体の意見として受け止められるため、他社製品を明確に批判する表現はブランドイメージの損失につながります。
②個人アカウントと間違えて発信してしまう
企業のSNS担当者が個人アカウントと間違えて日常的な投稿を企業アカウントから発信してしまうケースも炎上の原因になります。SNSユーザーは突然の無関係な投稿に困惑してリツイートなどの行動に移し、拡散されてしまうおそれがあります。万が一誹謗中傷を含むないようであればさらに炎上リスクは高まるでしょう。誤投稿を防ぐためには個人のデバイスと社用デバイスを紐付けないなどの対策を取る必要があります。
事例:【アカウント間違い】旅行サイト企業の炎上事例
企業の公式SNSアカウントが、個人用アカウントと誤認したまま、あるシンガーソングライターに対して「ぶさいく」といった不適切なコメントを投稿してしまう事態が発生しました。
この炎上の背景には、担当者がアカウントの切り替えミスを起こし、企業名義の公式アカウントから個人的な感情を含む投稿をしてしまったことが挙げられます。企業の公式アカウントでの発言は、ブランド全体のイメージを左右するため、こうした誤った投稿は多くのユーザーから批判を受ける原因となりました。
③個人情報や機密情報が適切に取り扱われていない
SNSを通じて個人情報・機密情報が漏洩するケースも後を絶ちません。悪意を持って漏洩させる場合だけでなく、従業員が個人アカウントで何気なく投稿した画像に顧客情報が映り込んでいて炎上につながったというケースなども見受けられます。従業員に対する日常的なSNS研修などを通じてリテラシーの向上を図る必要があると言えるでしょう。
事例:【情報漏洩】大手フィッチネスチェーンでの炎上事例
ある大手フィットネスクラブの従業員が、自身のSNSアカウントにて有名YouTuberの氏名を明かし、その人物が施設の会員であることを投稿したことで、プライバシーの侵害が問題視され、批判が集中しました。
この投稿により、SNS上では「会員情報を私的に公開するのは重大な情報管理の不備だ」といった指摘が相次ぎ、従業員の情報リテラシーの低さが企業としてのコンプライアンス体制への不信感に発展しました。炎上は広がり、企業側は公式サイト上で謝罪文を掲載する事態となりました。
④発信内容が不適切である
不適切な発信内容が火種となるケースも少なくありません。従業員個人によるイタズラ動画などが炎上するケースだけでなく、企業アカウントでも話題性や閲覧数を追い求めるがあまり、過激な投稿をしてしまう場合があります。多様化が進む現代では多方面への配慮が求められ、配慮を欠く投稿や微妙なニュアンスが不適切と捉えられる可能性も。SNSの拡散性の高さを今一度認識し、発信前には複数担当者でのダブルチェックを行うなど対策が必要でしょう。
事例:【ルッキズムを示唆?】大手生活用品メーカーの炎上事例
大手生活用品メーカーが駅で展開した広告キャンペーンが、「ルッキズム(見た目による差別)を助長している」としてSNS上で批判を集め、炎上する事態となりました。
このキャンペーンは、「カワイイに正解はない」というメッセージを伝えることを目的に、「中顔面6.5cm」「目と目の間が4cm」「出目」といった一般的に“かわいい”とされる基準を否定するような表現を用いていました。
しかし、多くのユーザーからは「なぜこのような表現で社内の承認が通ったのか」「知らなくてもよい言葉をあえて可視化する必要はなかった」といった疑問や違和感の声が寄せられました。
⑤従業員やアルバイトの言動が不適切である
バイトテロという言葉が生み出されるほど、従業員やアルバイトによる不適切な言動が大きな炎上を引き起こすケースが目立ちます。動機は「注目を集めたい」という気軽なものでも、実際に店舗の閉店や大幅な売上の下落など甚大な被害につながったケースもあり、見逃せないリスクのひとつです。従業員個人の高額な賠償請求を受けるなど大きな不利益を被る場合も珍しくありません。
また、実店舗での対応に不満を抱えたユーザーがSNSでネガティブな情報を拡散する場合も。SNSリテラシー研修だけでなく、そもそもの顧客対応研修を充実させることも炎上対策につながります。
事例:【バイトテロ】大手回転寿司チェーンでの炎上事例
大手回転寿司店では、アルバイト従業員が寿司ネタを舐める、湯飲みを舐めるなどの行為を行い、その映像がSNS上で拡散されました。これにより、企業の信頼性や衛生管理への疑問が広まり、消費者からの批判が殺到しました。
企業は、速やかに該当動画を削除し、公式に謝罪を行いました。さらに、企業のイメージ回復と再発防止のため、従業員教育の強化やSNSの利用ガイドラインの見直しなどの対応策を講じました。
⑥ハラスメントや労基違反を内部告発される
待遇等に不満を持っている従業員による内部告発が炎上を引き起こすケースもあります。ハラスメントや労基違反について投稿される場合もあり、企業ブランドの低下や採用への悪影響などが懸念されます。前提としてハラスメントや労基違反を行わないことはもちろん、風通しのよい社内風土を醸成する必要があるでしょう。
万が一内部告発があった場合は、再発防止策の公表など誠実な対応を心がける必要があります。後手に回った対応や責任逃れと捉えられる対応をしてしまうと二次炎上を引き起こす場合があるので注意が必要です。
事例:【内部告発】大手食品メーカーの炎上事例
ある大手食品メーカーが炎上する事態となった背景には、新卒社員に対する説明と実態の大きな乖離がありました。
企業側は「新築の社員寮を用意している」と説明していたものの、実際に用意されていたのは雨漏りのする老朽化した建物で、しかも複数人での共同生活を強いられる環境でした。
また、内定時に提示されていた給与から入社後に約3万円が減額されていたこと、さらに「オフィス勤務」としていた配属先が実際には工場勤務だったことなど、複数の条件で事前の説明と食い違いが生じていました。
こうした対応が不誠実だと受け取られ、SNS上で批判が噴出。情報は急速に拡散され、テレビやネットニュースなどでも大きく取り上げられる事態となりました。
最終的には内定辞退が相次ぎ、全体の9割以上の新卒社員が入社を取りやめています。
SNS炎上対策マニュアルと未然に防止するポイント
SNS炎上は企業にとって大きなリスクとなりますが、未然防止と対策を万全にすることで、被害を最小限に抑えることが可能です。
まずは、担当者がSNSの運用に関するルールを明確にし、投稿内容を事前にチェックして問題がないか確認しましょう。また、定期的に社員教育を実施し、適切なコミュニケーションが取れるようにすることも大切です。
炎上が発生した場合の対応は、迅速かつ適切に、必要に応じて謝罪や対策の発表をして、顧客との信頼回復に努めましょう。さらに、SNS投稿のモニタリングツールを活用することで、問題が拡散する前に対処することができます。
最後に、過去の炎上事例を参考にしながら、自社のリスクを分析して対策を練り、常に改善に取り組むことが重要です。
関連記事

炎上リスクを抑える7つのポイント
炎上リスクを抑えるためには、以下の7つのポイントを意識しましょう。
– 社内のSNSポリシーを策定し周知徹底
– 投稿前のチェック体制を整える
– 社員教育の実施
– 不適切な投稿の削除
– モニタリングツールの活用
– 適切なコミュニケーションスキルの習得
– 炎上事例を参考にした対策の検討
高効果&リスク回避の投稿術と活用方法
高効果かつリスク回避を目指す投稿術として、以下のポイントが挙げられます。
– ターゲット層に適した内容を発信
– 明確なメッセージと説得力のある事例を提示
– 適切なハッシュタグを活用
– ユーザーが共感しやすい投稿を心掛ける
– 問題が発生した場合の対策を事前に検討
これらの方法を取り入れて、効果的なSNS活用を行いましょう。
ユーザーとの適切なコミュニケーションの重要性
ユーザーとの適切なコミュニケーションは、企業のSNS活用において重要です。顧客の意見や質問に対して、丁寧かつ迅速な対応を行い、信頼関係を築くことが大切です。また、ユーザーとのコミュニケーションを通じて、自社の商品やサービスの魅力を伝える機会と捉え、効果的なマーケティング活動につなげましょう。
公式アカウントの運用ルールと教育体制
企業のSNS活用はマーケティングや情報発信に重要な役割を果たしますが、運用ルールや教育体制が不十分だと炎上リスクが高まります。そこで公式アカウントの運用ルールと教育体制を整備することが大切です。
まず、運用ルールを明確にし、投稿の内容や対象、担当者を決めることが必要です。これにより、投稿の方向性がぶれず、問題が発生しにくくなります。また、担当者が変わっても運用が継続でき、投稿の質が安定します。
次に、教育体制を整えることが重要です。従業員に対してSNSの運用方法や注意点を教え、定期的な研修を実施しましょう。これにより、トラブルを未然に防ぐことができます。
また、SNSのマニュアルやポリシーを作成し、社内で共有することが大切です。これにより、従業員が投稿の際に迷いが生じず、適切な投稿が続けられます。
最後に、運用ルールや教育体制の見直しを定期的に行うことが重要です。インターネットやSNSの状況は日々変化するため、適切な運用と対策を維持する必要があります。
公式アカウントの運用ルールと教育体制を整えることで、炎上リスクを減らし、企業のブランドを維持しましょう。
SNSの炎上の被害が拡大する場合の原因
SNSで炎上が起こった際に、被害が拡大してしまう原因として大きく以下の2つがあります。
- 状況把握の遅れ
- 初動のミス
状況把握の遅れ
炎上につながる投稿は、投稿直後からすぐに大きな批判を浴びるとは限りません。投稿後に一定の時間差があってから反発が広がるケースもあります。批判が起きていることに気づかず、対応が遅れてしまうと、炎上が手のつけられないほど拡大することがあります。また、担当者が問題に気づいても、上司への報告や対策の検討がスムーズに進まず、対応が遅れることで被害が大きくなることもあります。SNSでの炎上は、迅速な対応が非常に重要で、遅れるほど批判がエスカレートしてしまう点を意識しておく必要があります。
初動のミス
批判への対応や炎上後のアクションが原因で、二次炎上が発生してしまうケースもよく見られます。
例えば、問題となった投稿を削除したことでかえって不信感を招いたり、謝罪の内容やタイミングが適切でなかったために批判がさらに強まることがあります。ネットやSNS上の反応や論調を正確に読み取らずに対応を進めると、思わぬ形で火に油を注ぐ結果となってしまうことも少なくありません。だからこそ、なぜ批判が起きているのかを冷静に把握し、どのような対応が最善かを慎重に考えることが不可欠です。
炎上時に事態の本質を理解せずに対応した結果、さらなる批判と拡散を招く失敗例は依然として多く見受けられます。そうした二次炎上の事例から原因を学び、適切な対策を講じることが炎上防止には重要です。
SNS炎上発生時に被害最小化するための対処法&事後対策
炎上発生時は迅速かつ適切な対処が求められます。まずは炎上の原因や影響範囲を把握し、迅速な謝罪を行いましょう。謝罪は具体的で誠実なものが好まれます。また、その後のフォローアップも重要で、対策や改善策を策定し発表することが必要です。
事後対策としては、炎上の原因を分析し今後の対策に活かすことが大切です。状況や原因から学び、運用ルールや教育体制を見直しましょう。また、モニタリング体制の強化も重要で、炎上の兆候をいち早く察知し対処することができます。
さらに、関係者やお客様への情報提供や説明も重要です。適切な情報を発信し、信頼回復ができるよう努めましょう。
炎上対策は一度の改善で終わりではありません。状況や問題に応じて適切な対策を考え、継続的に実行しましょう。これにより、企業のブランドイメージを保ち、炎上のリスクを減らすことができます。
関連記事
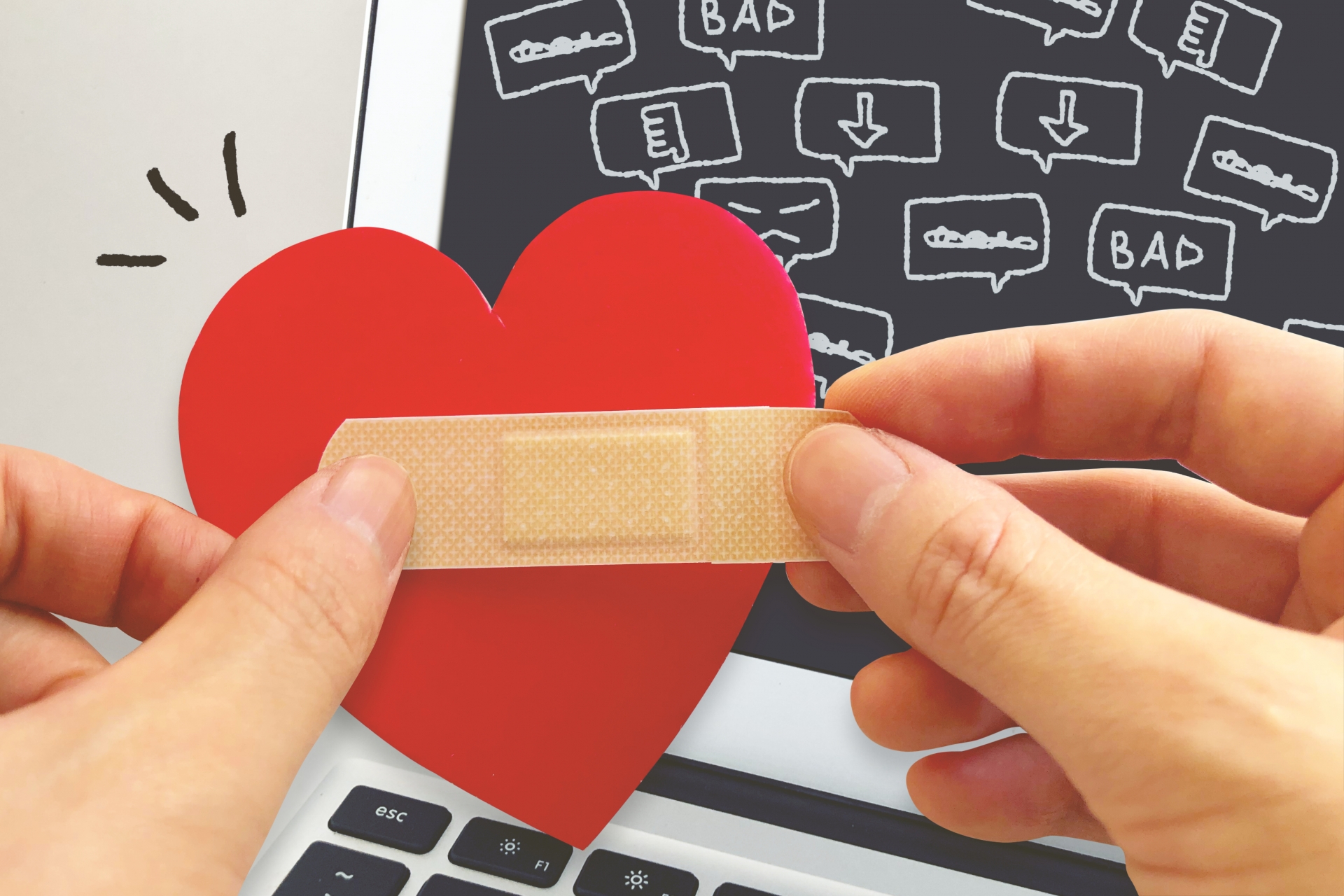



①炎上時の状況把握と関係者連絡体制
炎上が発生した際には、まず状況把握が重要です。投稿内容や拡散状況、影響範囲を把握しましょう。これにより対応のスピードや適切性が向上します。また、状況をリアルタイムで把握するために、専用ツールを活用することが有効です。
次に関係者連絡体制を整備することが大切です。発生時に迅速に対応するため、担当者や部門間での連携を密に行いましょう。また、外部の専門家や広報担当にも情報提供を行うことで、適切な対応が可能になります。
このような状況把握と関係者連絡体制が整っていれば、炎上対策が適切に行われることで企業の信頼を保ち、被害を最小限に抑えることができます。
②迅速な謝罪とフォローアップの重要性
炎上時には、迅速かつ適切な謝罪が大切です。謝罪が遅れると問題が拡大し、より多くの人に悪影響を及ぼすことがあります。そのため状況を把握し、早急に謝罪を行いましょう。
また、フォローアップも重要なポイントです。謝罪だけで終わらせず、具体的な改善策を提示し、誠意を示すことが大切です。これにより、顧客との信頼関係を回復し、不信感を払拭することができます。迅速かつ適切な謝罪とフォローアップを心掛け、企業の信頼回復に努めましょう。
③発信内容のチェックと適切な削除判断
企業のSNS運用において、発信内容のチェックと適切な削除判断が必要となってきます。炎上リスクを未然に防ぐために、投稿内容が問題の火種にならないよう確認することが重要です。
具体的な方法は次の通りです。
-投稿前に、担当者同士で内容を確認し合う
-投稿内容が自社のポリシーやルールに適しているかチェックする
-過去の炎上事例を参考に、顧客の反応を予測し調整する
また、投稿が拡散され炎上した場合、適切な削除判断が必要です。削除すべきかどうかを判断するポイントは以下の通りです。
-投稿内容が明らかに中傷や誹謗である場合
-顧客からの要望が多い場合
-投稿の正確さや適切さに疑問がある場合
ただし、削除する際には、「削除」という行為が逆に炎上を拡大させないか慎重に判断しましょう。
④炎上後の顧客対応とイメージ回復策
炎上後の顧客対応とイメージ回復策は、企業の信用を取り戻すために重要です。具体的な対策は以下の通りです。
1.迅速な謝罪と対応
炎上の発生を確認したら、できるだけ速やかに謝罪し、具体的な改善策を示しましょう。
2.顧客とのコミュニケーション
顧客からの質問や批判に対して適切かつ丁寧に回答し、関心を持って対応することが大切です。
3.火種の特定と原因解説
炎上の原因を特定し、対策を実施して未然に防ぐための教育を徹底しましょう。
4.イメージ回復のための宣伝活動
該当アカウントだけでなく、他のメディアや広告を活用して企業の良い面を発信しましょう。
これらの対策を適切に実施することで、企業のイメージ回復が可能となります。
企業のSNS炎上対策ツールとサービスの活用法
炎上リスクを低減するために、炎上対策ツールとサービスを活用しましょう。具体的な活用法は以下の通りです。
1.状況把握と分析
SNS専用のモニタリングツールを利用することで、投稿の拡散状況や顧客の反応をリアルタイムで確認できます。
2.対応体制の整備
専門のサポートサービスを利用し、迅速かつ適切な対応が行える体制を整えましょう。
3.教育と従業員の認識向上
定期的なセミナーや研修を通じて、従業員のSNS運用に関する意識を向上させることが重要です。
これらのツールやサービスを活用することで、企業のSNS運用がより安全で効果的となります。
モニタリングツールの選定と導入方法
モニタリングツールを選定する際には、自社のSNS運用やマーケティング戦略に合ったツールを選びましょう。無料で利用できるツールや、有料ですが多機能なツールもありますので、各ツールの特徴を理解し、比較検討してから選ぶことがポイントです。また、導入後は従業員への教育を実施して、適切な活用方法を伝えましょう。
具体的な導入方法としては、まず、利用したいSNSアカウントとツールを連携させます。次に、ツール上でモニタリング対象のキーワードやアカウントを設定しましょう。その後、定期的にツールでの分析結果を確認し、必要に応じて対策を立てます。このように、モニタリングツールを活用することで、炎上リスクを減らすことが期待できます。
関連記事


事前リスク分析と炎上発生の予兆検知
事前リスク分析に取り組むことで、炎上問題の未然防止に繋がります。まずは自社のサービスや商品に対する顧客の意見をSNSなどで調査し、ポイントを把握します。次に、その意見を分析してリスク要因を特定し、対策を立てましょう。
炎上発生の予兆検知には、定期的にSNSの投稿やコメントをチェックして批判的な意見や誹謗中傷がないか確認することが重要です。また、モニタリングツールを活用して、予兆を感知することができます。これにより、早期対応が可能となり、炎上事態を最小限に抑えることが期待できます。
企業内の炎上対策ポリシーの策定と教育
企業内で炎上対策ポリシーを策定し、従業員に周知徹底することが大切です。ポリシー策定の際には、炎上リスクの発生源や対処方法を明確にし、具体的なルールや指針を定めます。また、定期的な教育を実施し、従業員が適切な対応ができるよう体制を整えることも、重要なポイントです。
一方で、炎上対策ポリシーの効果を確認するために、定期的なモニタリングとフィードバックが欠かせません。こうした取り組みによって、企業全体で炎上対策の意識が高まり、リスク低減に繋がります。
関連記事

自社や周囲のSNS炎上ケースから学ぶ
過去の自社や他社の炎上事例を参考にし、原因や対応策を分析することは、炎上対策の向上に役立ちます。具体的な事例を学ぶことで、自社でも同じリスクが発生しないように、適切な対策を立てることができます。また、他社の炎上ケースから教訓を得て、自社のSNS運用に活かすことが重要です。
おすすめのSNS炎上対策モニタリングツール
適切なSNS炎上対策を講じたい場合は、エフェクチュアルにお任せください。エフェクチュアルではSNSをはじめとする2000以上のメディアを24時間365日監視する「ミマモルン」というサービスを提供しています。炎上リスクとなるネガティブな投稿をいち早く検知し、デイリー・マンスリーレポートで状況を確認可能。実際に炎上した場合の記者会見の手配などのサポートまで行います。SNS炎上に関わる対策を一気通貫で行いたい場合は、ぜひ気軽にお問い合わせください。
最後に: 炎上対策の徹底が事業成長につながる
炎上対策を徹底することで、事業成長に繋がります。リスク低減は信頼や評価向上にもつながり、結果としてビジネスに貢献することになります。炎上対策を行ううえで、まずは自社でできることから始めましょう。さらに詳しい情報や対策方法を知りたい方は、セミナーや相談サービスを活用してみてください。
SNS炎上対策はモニタリングツールを活用することで効果的に対策できます。株式会社エフェクチュアルではMimamorn(ミマモルン)というモニタリングツール(投稿監視ツール)を提供しております。Mimamornは、特定のキーワードを登録し、Web上でのリスク通知基準に合致する投稿を監視します。また、定量分析レポートを作成することが可能で、炎上発生時には適切な対処法を支援します。有人監視で対応するため、メディア数は無制限で広範囲のリスク検知が可能です。監視したい媒体、キーワード数、予算などに応じて柔軟にカスタマイズもできるので、ビジネスの規模やニーズに合わせて最適なプランを選択できます。料金は初期費用無料で、月額50,000円から利用できるので、コストパフォーマンスに優れているのもメリットの1つです。多くの企業がアクセスしやすい価格設定となっています。
Mimamornの主な機能は以下の通りです。
– キーワードに基づく投稿監視
– リスク通知基準に合致する投稿の抽出
– 定量分析レポートの作成
– 炎上発生時の適切な対処法の支援
– 予算に応じたカスタマイズ
Mimamornを活用することで、効率的かつ確実な投稿監視を行うことができ、安心してビジネスを展開できます。また、企業のWEBリスクマネジメントを専門的に行っており、個人や法人のさまざまな悩みに対応しております。風評被害対策や社内教育のためのセミナーなども幅広くご提供しておりますので、ご興味がある方はまずはお気軽にお問い合わせください。
Mimamornの詳細は下記バナーをクリック!


